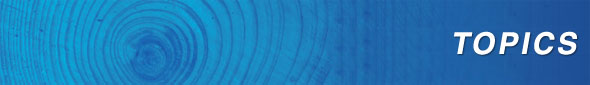
[座談会]疫学研究を臨床に結びつけるために
[インタビュー]疫学研究と臨床の交流の場を求めてもご覧ください

| 司会: | 寺本民生 | (帝京大学医学部内科) |
| 磯 博康 | (大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学) | |
| 大橋靖雄 | (東京大学大学院医学系研究科生物統計学/疫学・予防保健学) | |
| 桑島 巌 | (東京都老人医療センター) | |
| 堀 正二 | (大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学) |
1990年代に確立されたEBMという手法は,その後の夥しい臨床試験データとともにわが国に導入され,医療現場に多大な影響を与えてきた。わが国においても,日本人のエビデンス蓄積の必要性が認識され,医師主導の臨床試験も数多く実施されるようになった。それらの動きに伴い,対象母集団の基本情報が介入試験実施の前提として重要視されるようになった。疫学観察研究の成果は,いまやEBMを支える両輪の一つとして,臨床試験の評価と適応に欠くことのできない位置を占めつつある。ここでは「循環器疫学サイト epi-c.jp」の編集委員により,疫学研究が臨床に果たす役割と可能性について討議してもらった。
 寺本 疫学研究はなかなかなじめなかったのですが,大規模臨床試験の結果が臨床の場でどれだけ生かせるかを考えるためには,疫学の知識によって解釈する必要性を感じるようになりました。今日は疫学研究を臨床医はどうみていったらよいのかを話していければと思います。
寺本 疫学研究はなかなかなじめなかったのですが,大規模臨床試験の結果が臨床の場でどれだけ生かせるかを考えるためには,疫学の知識によって解釈する必要性を感じるようになりました。今日は疫学研究を臨床医はどうみていったらよいのかを話していければと思います。
最初に磯先生に循環器疫学の現状についておおまかな紹介をしていただきたいと思います。
磯 循環器疫学では,フラミンガム研究とSeven Countries Studyがパイオニア的な研究と位置付けられます。日本でも久山町研究,秋田県の井川町研究や大阪の勤労者コホート研究が昭和30年代後半からはじまっています。フラミンガム研究からは危険因子という概念が,久山町研究や井川町研究などからは日本の脳卒中の実態が示されました。
一方,癌の疫学あるいは生活習慣病の疫学研究として,もう少し大がかりな疫学研究が20年ぐらい前から世界各国ではじまりました。米国では10万人規模の看護師のコホート研究であるNurses’ Health Studyや,男性の歯科医師,獣医など5万人規模のコホート研究であるHealth Professionals Studyなどです。
それまではフラミンガム研究など循環器疾患の研究は数千人からせいぜい1万人ぐらいの規模でしたが,栄養や運動などの生活習慣を危険因子として評価するために大規模になってきました。日本では国立がんセンターと国立循環器病センターに大学などの研究機関が加わったJapan Public Health Center-Based (JPHC) Prospective Studyという生活習慣病のコホート研究があります。また名古屋大学が中心になって全国の衛生・公衆衛生の研究者が行っているJapan Collaborative Cohort Study for Evaluation for Cancer Risk (JACC)も10万人規模の大きな疫学研究です。茨城県でも10年前から約10万人規模でコホート研究が行われています。
最近では従来の数千人規模のコホート研究と,10万人規模のコホート研究をメタアナリシスする研究として,大橋先生が事務局をされているJapan Arteriosclerosis Longitudinal Study (JALS)研究があります。
寺本 いま磯先生からいくつかの疫学研究が紹介されましたが,桑島先生は臨床の側から疫学をどのようにみていますか。
 桑島 疫学というと,やはりフラミンガム研究がわれわれ循環器医にとってはすぐに思い浮かぶし,日常診療で非常に参考になっています。
桑島 疫学というと,やはりフラミンガム研究がわれわれ循環器医にとってはすぐに思い浮かぶし,日常診療で非常に参考になっています。
フラミンガム研究で40年も前に提起された危険因子の重複(clustering)という概念は,近年注目されているメタボリックシンドロームに結びついています。血圧に関しても,フラミンガム研究などの疫学研究から,血圧と心血管合併症の関連について知見が得られるようになりました。
しかし,臨床医はこれまでどちらかというと疫学研究を軽視する傾向がありました。高血圧の分野では,すでに20年前に疫学研究により血圧は低い方が心血管合併症の発症が少ないことが報告されていたにもかかわらず,多くの臨床家は「治療」は別の問題,血圧はあまり下げなくてもよいと考えていたのです。しかし,最近になってようやく血圧は下げるべきだと考えられるようになってきました。
疫学的知識が治療に結びつかなかった理由の一つは,よい治療がなかったために血圧や脂質値を下げることができなかったからです。いまはスタチンがでてきて,降圧薬もよいものがでてきたため,血圧や脂質を厳格に下げることで心血管合併症を予防できることが証明されたのです。つまり疫学の正しさがやっと治療学で証明されたということです。
一方,私は最近,ランダム化比較試験(RCT)は限界にきているという印象をもっています。治療学が発展し,試験方法もPROBE法なども行われるようになってきたため比較しても群間に差がつかなくなりました。いまこそ疫学の成果を踏まえた臨床研究の構築が大事なのだといえます。
「文化」としての疫学,「文化」を反映する疫学
寺本 堀先生,いかがですか。
 堀 疫学には各国のバックグラウンドの違いがでるように思います。スウェーデンやノルウェーでは,国勢調査のようなもののなかで健康データを一緒に集めていて,これが北欧の疫学のベースの1つになっています。北米ではフラミンガム研究がスタートした後,カナダのマクマスター大学で「疫学」を学問体系にする取り組みがはじまりました。
堀 疫学には各国のバックグラウンドの違いがでるように思います。スウェーデンやノルウェーでは,国勢調査のようなもののなかで健康データを一緒に集めていて,これが北欧の疫学のベースの1つになっています。北米ではフラミンガム研究がスタートした後,カナダのマクマスター大学で「疫学」を学問体系にする取り組みがはじまりました。
一方,日本はというと,いまだに「この病気が何人いるか」と聞いても数字が出てこない,きわめて特異な国です。自分の実態を知ることに関心をもってこなかったといえます。医療というのは自分の目の前に来た患者さんを治すこという意識が非常に強くて,関心が「個」だけに向かっていた。
疫学というのは文化だと思うのです。ライフスタイルが疫学のベースを作っているのです。どの病気が何人いるのかも知らないということは,自分の国にどんな文化があるのかを知らないということです。欧米と日本では実態が違います。日本はどうなのかということをもっと知らないと,あらたな治療法が生まれてきても臨床の場で生かせません。このことに皆が気付きはじめているのではないかと思います。
寺本 あるライフスタイルのなかで起こってくる病気というのがあるわけですから,日本のなかで起こってくることと,欧米で起こってくることは違うわけですね。大橋先生,いかがですか。
大橋 大変刺激的なお話です。治療学が進んで疫学データが脚光を浴びるというのはまさにそのとおりです。
また,疫学に文化の違いがでるということには大賛成です。日本は農耕民族の文化で,周りと合わせることを考えてきました。それが狩猟民族とはまったく違いデータに基づいて行動するということはあまりなかった。私の先生である開原成允先生が「それがデータベースができなかった理由である,文化の違いだ」といわれていました。国の統計の利用度は,日本はOECD参加国のなかで最低です。
しかし,いま日本の疫学は大変おもしろい時代にはいっています。日本では健診データをベースに疫学研究を行っています。このような手法をとっている国は世界にあまりないと思うのです。疫学が大きく変わってきて,健康増進にもリンクしていく。ダイナミックな時代になってきています。
リスクファクターと『ベネフィット』ファクター
寺本 癌や生活習慣病の疫学では住民健診データから行っているのですね。
磯 日本では自治体の住民健診をベースにして研究するという手法が多いですね。欧米では地域でランダムサンプリングし,電話でリクルートして個別的に健診するという手法がとられています。日本でもそのようにできないことはないとは思いますが,いままでの文化的な背景が違うために一般的には行われていません。集団健診を活用して研究するという手法が使われ,その伝統を踏襲しているといえます。
寺本 生活習慣の研究のなかで非常にインパクトがあるなと思ったのは,磯先生がお示しになった,魚の摂取と冠動脈疾患を調べたJPHCの結果です(Circulation 2006;113:195-202)。なぜ調べようと思われたのですか。
 磯 魚や海獣類を多食しているグリーンランドエスキモーのコホート調査では心筋梗塞が少ないことが報告されていました(Int J Epidemiol 1988; 17: 514-19)。またKromhoutらがオランダ人の20年間のコホート研究により,魚を食べない人よりは週に1回か2回食べる人のほうが心筋梗塞は少ないと報告しています(N Engl J Med 1985; 312: 1205-9)。
磯 魚や海獣類を多食しているグリーンランドエスキモーのコホート調査では心筋梗塞が少ないことが報告されていました(Int J Epidemiol 1988; 17: 514-19)。またKromhoutらがオランダ人の20年間のコホート研究により,魚を食べない人よりは週に1回か2回食べる人のほうが心筋梗塞は少ないと報告しています(N Engl J Med 1985; 312: 1205-9)。
日本人は魚をよく食べる民族で,米国と比べても心筋梗塞の死亡率は4分の1です。Seven Countries Studyでみると,総コレステロール値は日本は非常に低いのですが,各国の間でコレステロール値が同じ場合でみても心筋梗塞による死亡率は明らかに低い。コレステロール値だけでは心筋梗塞の国の差は説明できないと判断されます。
JPHCの結果では,週に1,2回食べている人と毎日食べている人で比較したところ,毎日食べている人で,リスクが半減しているのです。欧米人では週1,2回の摂取で心筋梗塞が半分になることがわかっていたのですが,毎日食べればさらに半分になるという可能性が出てきました。
堀 魚食に関しては“リスク”ファクターではなくて“ベネフィット”ファクター,よいファクターですよということを,日本からもっと発信しなければいけないと思うのです。日本は世界でもっとも長寿の国です。なぜ日本人が長寿なのか。その“ベネフィット”としてわかっていることは,リスクファクターの逆のものとして,世界に示すべきだと思うのです。
寺本 私もそう思います。日本の食生活はかなり変化が起こっていて,いまの子どもたちはあまり魚を食べなくなっている,つまりよい文化をいま失いつつあるのです。
磯 あまり一般的ではありませんが,英語ではプロテクティブファクターという言葉があります。
堀 もっと積極的な意味を持たせたいですね。
RCTを疫学から読む
寺本 疫学,統計の先生に伺いたいもう1つの問題は,ランダム化比較試験(RCT)についてです。臨床研究の読み方は,先生方はどのように考えていらっしゃいますか。
 大橋 RCTでは一次評価項目をきめて,それが証明できるサンプルサイズを設定しています。つまり,一次評価項目以外に関しては確証とはなりません。データの読み方は疫学と同じで,試験が行われたのはどういう集団であるのかを考える。サンプルは選ばれているのですから,それが一般化できるのかどうかが最大の問題です。
大橋 RCTでは一次評価項目をきめて,それが証明できるサンプルサイズを設定しています。つまり,一次評価項目以外に関しては確証とはなりません。データの読み方は疫学と同じで,試験が行われたのはどういう集団であるのかを考える。サンプルは選ばれているのですから,それが一般化できるのかどうかが最大の問題です。
疫学には医療の問題点を指摘する役割もありますが,よい治療が適切に行われているかを評価するのも,疫学の重要な役割です。そのようなアウトカムリサーチにはデータを集約できるシステムが必要ですし,薬剤の製造販売後の薬剤疫学的な研究も必要です。つまり疫学は医療の最初と最後のところ,問題点の指摘と評価に役割があります。そのように使ってはじめてRCTの結果をどう読むかにつながります。
RCTがどんどん難しくなっている点についてですが,サロゲートエンドポイントをどう評価するかというのは,疫学から考えなければなりません。そのような臨床試験と疫学との相互作用がありうるし必要であると思います。
堀 RCTは臨床研究の手法として最終的なものでしょうか。それとも将来的には違う手法がでてくるのでしょうか。たとえば全国民の登録がきちんとなされて,服用している薬,その時期,その背景情報も全部データベース化されたならば,それで治療法の評価研究はできますね。そうだとすると,RCTという,抽出された集団で行う研究手法はオールマイティではないということになりますね。
大橋 おっしゃるとおりRCTはオールマイティではありません。しかし,RCTは妥当な(バイアスのない正確な)結果を常に出せるので大きな意義はあります。それに代わるような,データベース構築ができればRCTはなくてもよいのですが,それは現在の知識水準では無理だろうと思います。特に薬剤の効果を見るにはRCTは残るでしょう。しかし,RCTでは選ばれた集団のなかでの効果は推定できるけれども一般化の保証は必ずしもない。この欠点は意外に理解されていません。その欠点を補うのが疫学です。
新しい疫学研究の可能性
寺本 フラミンガム研究の特異性はどのようなところにあるのでしょうか。
磯 フラミンガム研究は内科の研究者が中心ですが,最初から統計学者も入っています。国家プロジェクトとして多彩なバックグラウンドを有する研究者が,循環器疾患の自然歴の探究や危険因子の同定を長期計画にもとづいて行ったのが特徴です。
一般に公衆衛生の研究者は公衆衛生の分野で,臨床の先生はその臨床の分野で,個別的に研究を行ってきました。そのため,医学部の教育では疫学とか保健統計といったものは学生にとっても非常にとっつきにくかったわけです。ただ,日本でも疫学研究に対する社会的な要請も大きくなってきましたし,状況がだんだん変わってきているように思います。
桑島 以前の疫学というのは,断面調査という意味合いが強かったのではないでしょうか。長期間にわたって追跡するというのはフラミンガム研究以降ではないでしょうか。
磯 そうですね。
桑島 疫学研究の問題点として,住民の移動が少ないことを前提にしている点ですね。現代は住民が非常に移動しやすくなっていますが,その補完はどのようにやっているのでしょうか。
磯 日本で長期間のコホート研究を行っているところは,住民の移動の少ないところが多いですね。大都市の真ん中で行うことは難しい。
桑島 企業の健診データは意外と生かされていませんね。定年退職後のフォローが不十分でイベント発生を追うことができないからでしょうか。
大橋 一部の企業で行われています。健保のデータを疫学研究として本格的に解析できるとポテンシャルはあると思います。
寺本 堀先生がいわれたように,登録がきちんとされていて,フォローアップできて,最終的なエンドポイントまでが追いかけられるようなシステムができると,RCTがなくともいろいろな問題点を見いだすことができるはずなのですね。
大橋 観察研究の解析方法が,この10年間で急速に進んでいますからできる可能性はあります。疫学研究からの統計手法の開発の一例は,ロジスティック回帰分析です。これはフラミンガム研究において,Jerome Cornfieldという統計家が発明したものです。最近は観察研究から因果的な効果を推定しようという試みが盛んに行われています。データベースを構築するときには,データの蓄積とともに,それを解析する方法論も開発しなければなりません。
疫学と臨床の相互作用から生まれてくるもの
寺本 臨床から疫学に対する希望,期待は非常に大きいのですが,疫学の先生たちから臨床医に対して,何かメッセージはありますか。
磯 以前ですと臨床研究を行ってしまった後にデータをどう解析したらよいかを,統計家に相談にいっていたのですが,最近は最初から臨床統計家が入るようになり,疫学,統計学の研究者と臨床の先生方が一緒になって互いに乗り入れながら研究を行うようになってきました。そうすることによって,臨床研究から疫学研究へ,疫学研究から臨床研究へというサイクルができあがるのだと思うのです。
堀 臨床医と疫学の先生との間にもしギャップがあるとすると,私たち臨床医は,疫学からデータがでてきても,メカニズムが説明できないと受け入れないのです。理屈がつけば,臨床医は納得して受け入れます。ですから疫学と臨床の間を何かで埋めないといけない。これはわれわれの仕事ではないかと思います。
大橋 基礎研究者の課題でもありますね。
寺本 疫学でわかってきたいくつかの因子に関しても,それを基礎科学の面から解明するというステップが必要なのでしょうね。フラミンガム研究で血清コレステロールと冠動脈疾患の関係が発表されましたが,そのころ臨床からは,リポ蛋白の中のLDL分画がどうも悪そうだというような実験的なデータがではじめていました。これをうけてフラミンガム研究ではLDLが高い人の予後を調べました。また,フラミンガム研究からHDLが防御的に働くことが示されると,今度はHDLの基礎研究がはじまりました。このように互いに高め合っている。疫学がどのように臨床に生きてきているのかを一般臨床の先生方にしめしていくのが,このサイトの持っている意義なのではないかと思っているのです。大橋先生,最後にコメントをいただけますか。
大橋 メカニズムを解明しながら,いまだわかっていないところを次の研究で明確にしていく。そういう立体的な構図が見られるとよいですね。
寺本 循環器疫学の成果を収載するこのサイトでも,そういう形での動きのある疫学を,ぜひアピールしていただければよいのではないかと思います。本日はどうもありがとうございました。
[インタビュー]疫学研究と臨床の交流の場を求めてもご覧ください
